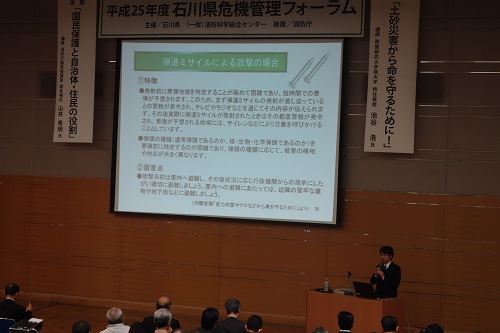▧ 千坂校下自主防災会は、平成27年7月9日(木)午後7時から役員会を開催、8月23日実施予定の台19回千坂校下防災訓練について協議した。
協議議題
- 千坂校下防災訓練実地要項
- 千坂校下防災訓練進行予定表
- 防災訓練会場(千坂小学校体育館)
- (千坂公民館)
- 図上訓練会場
- 二次避難参加者数(依頼)
- 町会別参加整理券配布一覧表
- 避難・災害等情報集計表

千坂校下町会連合会
シェイクアウトいしかわ
参加者募集 平成27年7月10日(金)午前11時
▧ 午前11時に県内で大地震が発生した想定で、県民が一斉に、それぞれの場所で安全行動を行う訓練です。ぜひ、ご参加ください。

千坂校下町会連合会
▧ 平成26年7月17日(木)午後7時〜標記役員会を開催し、以下の項目について原案について承認し、8月24日千坂校下自主防災会主催による防災訓練を実施することとした。
- 第18回千坂校下防災訓練について(依頼)
- 第18回千坂校下防災訓練実施要項
- 第18回千坂校下防災訓練進行予定表
- 千坂校下自主防災会役員(組織票)及び関係者の主な役割
- 千坂校下自主防災会組織の編成とおもな役割
- 第18回防災訓練会場 はしご車試乗体験 起震車体験
- 図上訓練会場
- 災害図上訓練グループ分け表
- 第18回千坂校下防災訓練参加者数(依頼)一覧表
- 避難・災害等情報集計用(町会用) (班長用)
- ひなん済 (訓練用)
- 町会別訓練参加整理券配布一覧表
- 防災マップ記載事項
- 各町会一時避難場所一覧表
千坂校下町会連合会
「県民一斉防災訓練(シェイクアウトいしかわ)」への参加について(お願い)
千坂校下地域住民
各 位
石川県危機対策課長
千坂校下自主防災会会長
▧ 東日本大震災において、住民一人ひとりの「自助」が被害の軽減につながるという、自助の重要性が改めて認識されたことから、本県では、昨年度初めて、全ての県民を対象とした「県民一斉防災訓練(シェイクアウトいしかわ)」を実施致しました。この訓練は、「しゃがむ」 「隠れる」 「じっとする」といった「安全行動」うぃ約1分間行うもので、どこでも、誰でも、気軽に参加する事ができる訓練であります。
▧ つきましては、校下の皆様におかれましては、訓練の趣旨をご理解のうえ、下記によりご参加下さいますようお願い申し上げます。
記
訓練日時 : 平成26年7月15日(火) 午前11時

避難所開設訓練(千坂校下防災訓練から)
千坂校下町会連合会
▧ 千坂校下自主防災会では下記により標記総会を開催致します。万障お繰り合わせの上ご出席賜りますうご案内申しあげます。
記
1.日 時 平成26年4月20日(日) 午後16時50分から
1.場 所 千坂公民館 2階ホール
1.議 題 (1)平成25年度事業報告並びに収支決算報告
(2)平成26年度事業計画並びに収支予算(案)
(3)その他

柳橋川の桜(千木町地内)
「ソメイヨシノ」の由来、“江戸染井村の植木職人が交配し「吉野桜」の名で 売り出したことによる”らしく単純ともいえば単純だが、苗字の由来のように、地名の影響 をうけているのがわかる。
千坂校下町会連合会
【講演】 「土砂災害から命を守るために!」
講師 池谷 浩 氏
(政策研究大学院大学 特任教授)

【内容】
▧ 災害とは : 「異常な自然現象や人為的原因によって、人間の社会生活や人名に受ける被害」を言う。土砂災害を引き起こす誘因となるものには、豪雨、地震、火山噴火など誘因の発生が多発している。
▧ 石川県の土砂災害危険箇所数 ・土石流危険渓流=2002カ所 ・地すべり危険箇所=420カ所 ・がけ崩れ危険箇所=1841カ所 計 4263カ所 ・うち 警戒区域設定済み箇所 3320カ所(2013.10.31時点)
▧ 土砂災害とは :: 土砂の移動現象(たとえば 土石流、地すべり、がけ崩れ、火砕流、溶岩流、火山泥流など)によって生ずる災害のこと。
▧ 最近の主な自然災害には、・2010.10過去に例のない記録的大雨(奄美大島の豪雨被害) ・2011.1 300年ぶりのマグマ噴火(新熱岳=霧島山の火山噴火) ・2011.3 M9.0の超巨大地震(東日本大震災) 2011.9 広域、長時間の豪雨(台風12号災害) ・2012.7 九州北部豪雨災害(阿蘇地方の土砂災害)
▧ 土砂災害の特徴 1.現象の発生予測が困難 2.発生した現象の速度がはやい・・・発生してからの避難は困難、破壊力が大きい。 3.発生頻度がそれほど大きくないので、住民の間に『正常化の偏見』が生まれている。・・・自分のところだけは大丈夫。 4.災害情報がうまく伝わらない・・・停電など
▧ 平時の防災情報と防災意識 ▧
・ 土石流とはどのようなものなのかは1997年に隣町の鹿児島県の出水市で発生した土石流災害を知って、土石流が恐ろしいものと認識していた。また、集川なは「土石流危険渓流」という標識があり、アンケート回答者の半数は「土石流危険渓流」があることを知っていた。
・ しかしほとんどの人は自分のところで出水市と同じ土石流災害が起こると思っていなかった。むしろ別の地区の法が気になっていたところも伺える。
・ 住民は皆土石流の発生の危険性は考えていなかった。特に高台には土石流がくるとは全く考えていなかった。
・ 危険区域のマップは無し。防災訓練も特にしていなかった。
▧ 対策方法 ▧
・ 行政の担当者の皆さんはもちろんのこと住民の皆さんにも『正常化の偏見』をなくしてもらうよう努力する。
・ 危ないところには行かない。
・ 自分の住んでいるところについて平時から土砂災害に対して安全かどうかを調べておく。
▧ まとめ ▧
・ 土砂災害は多様な原因、多様な現象そしてブラックボックスがある(予知予測困難)。=平時の対応が大切(知らせる努力と知る努力)。
・ 広域、同時多発など行政の対応に限界のある災害(住民の防災意識に期待)。=近くで楽しい避難(早めの避難)。
・ 専門性が強い現象だが専門家は少ない(住民の自助・共助が大切)。=何もしなければよかったと思う気持ち。
千坂校下町会連合会
【講演】 「国民保護と自治体・住民の役割」
講師 : 山井秀明 氏
(消防庁防災か国民保護室 課長補佐)
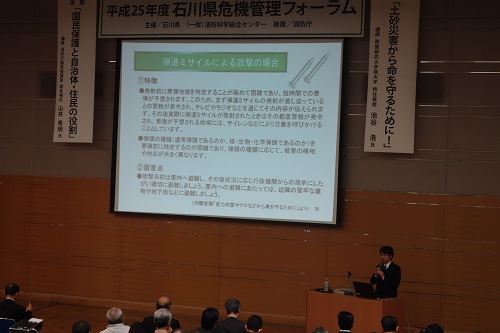
【内容】
▧ 私たちの社会を揺るがす危機
○ 自然災害(地震、津波、豪雨、暴風、豪雪・・) ○ 大規模事故など(大火災、爆発、列車事故、海難・・) ○ 感染症(SARS,鳥・新型インフルエンザ・・) ○ 国際的なテロn動向、北朝鮮情勢= あってはならない事態から国民を保護する仕組みが必要
▧ 国民保護の意義
○ 万一、武力攻撃や大規模テロが起こった場合に、正確な情報を把握し、住民に伝え、住民が正しく避難できるようにする。 救援、武力攻撃災害への対処を行う。
○ 国、県、市町村、住民などが協力して、住民を守るための仕組み
○ 住民の生命や財産を守るという意味では、地方公共団体・消防の本来の役割とも言える。
▧ 国民保護措置の3つの柱
○ 住民の避難 (情報の伝達、避難の実施)
○ 避難住民の救援 (収容施設の供与、食品等の提供、医療の提供)
○ 武力攻撃災害への対応 (消火、救助、 警戒区域の設定、避難の指示)
千坂校下町会連合会
▧ 石川県・消防科学総合センターが主催する標記フォーラムが平成26年2月1日(日)午後1時30分から石川県地場産業センター新館コンベンションホールにおいて、400名が参加して開催された。
プログラム
13:30 主催者あいさつ
13:35〜14:15 講演「国民保護と自治体・住民の役割」
講師 山井 秀明 氏
(消防庁防災課国民保護室 課長補佐)
14:25〜15:30 講演「土砂災害から命を守るために!」
講師 池谷 浩 氏
(政策研究大学院大学 特任教授)

千坂校下町会連合会